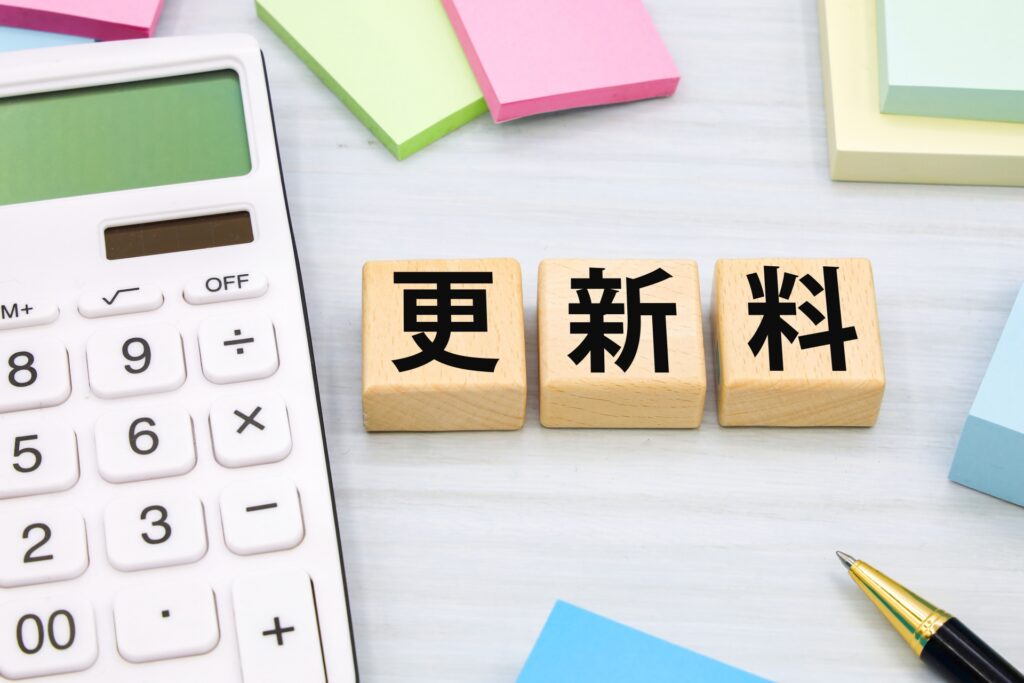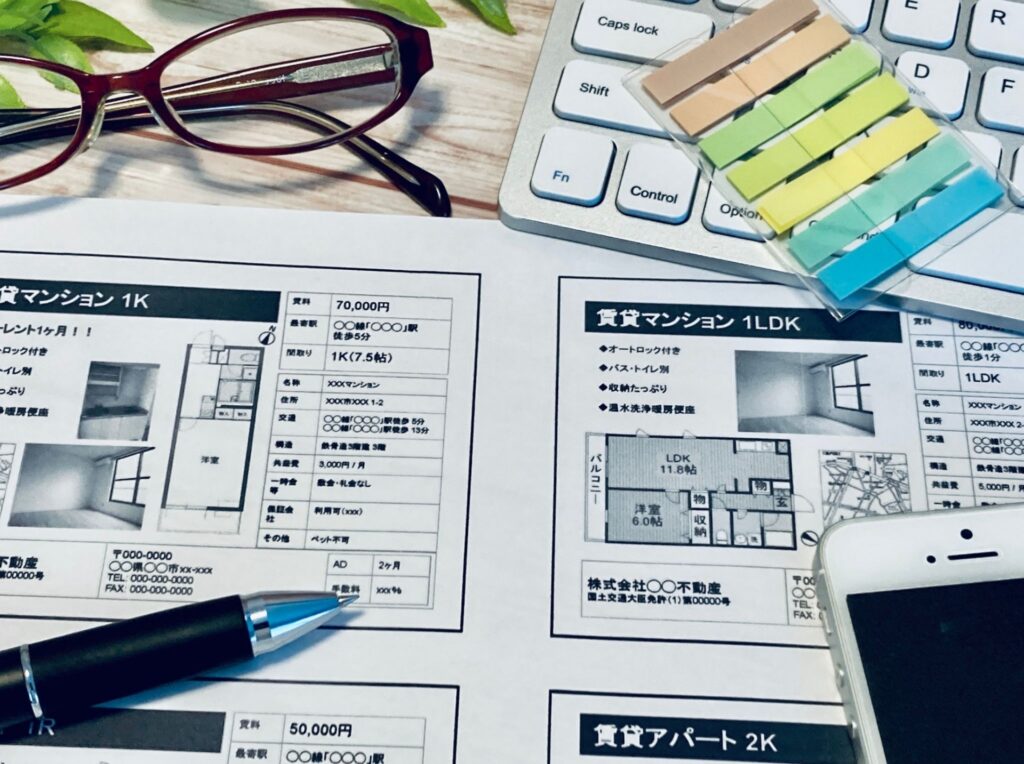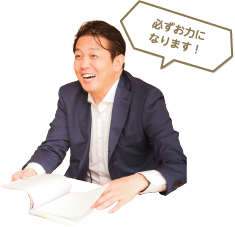借地権の更新料について悩んでいる方は少なくありません。「支払う義務があるのか」「提示された金額は適正なのか」「支払えない場合はどうすればよいのか」といった疑問を抱えている借地権者も多いでしょう。ここでは、借地権の更新料の法的位置づけから相場、計算方法、そして地主との交渉のポイントまで、借地権者が知っておくべき情報を詳しく解説します。
借地権の更新料とは
借地権の更新料とは、借地権の契約更新を行う際に借地権者が地主(貸主)へ支払う一時金のことです。法律上の明確な義務ではありませんが、契約の円滑な更新や地主との良好な関係維持のために慣習的に支払われることが多くなっています。
借地権更新のタイミングと更新料の発生理由
借地権には存続期間があり、期間が満了すると契約の更新もしくは終了を選択しなければなりません。更新方法には「合意更新」と「法定更新」の2種類があります。どちらの方法であっても、更新料が発生するのが一般的です。
■合意更新のときの取扱い
……更新前の契約書をベースに交渉により、更新料を発生させないことも含めて合意して定めます
■法定更新のときの取扱い
……当初の借地契約に更新料特約があるときに限って支払義務が生じるとするのが基本です
▼こちらの記事も参考になります
借地権(建物所有目的の土地賃貸借契約)の更新にあたって|借地人さん向け
借地権更新料の相場と計算方法
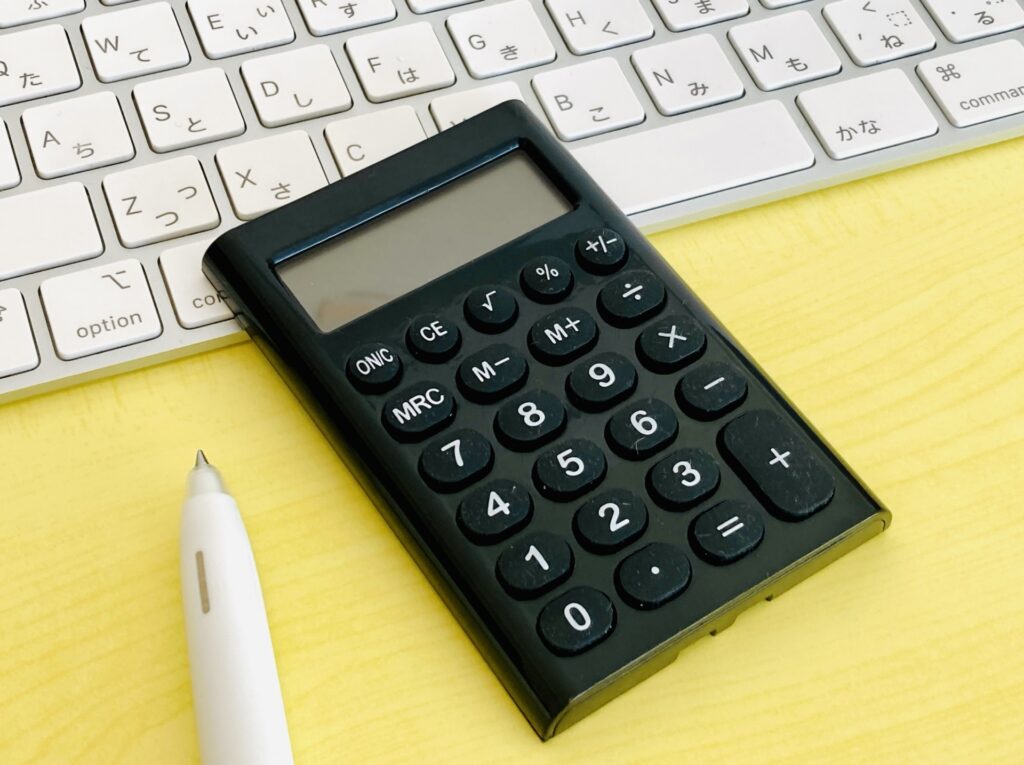
借地の更新料は地域や物件の特性によって異なりますが、一般的な相場や計算方法を知ることで、適正な金額を見極める目安になります。更新料は更地価格を基準に算出されることが多く、その料率や計算方法を理解することが交渉の第一歩となります。
基本の計算方法(更地価格の3~5%)
借地権の更新料は、一般的に更地価格の3%から5%とされます。この計算の基礎となる借地の更地価格の評価は、路線価(相続税・贈与税を計算するときの評価額)や、国土交通省が定める公示地価につき、各地の借地権割合である60%から80%ほどとなるのが一般的です。
【例】路線価5,000万円・借地権割合80%・土地の場合
- 更新料の割合が3%の場合:5,000万円 × 80% × 3%=120万円
- 更新料の割合が5%の場合:5,000万円 × 80% × 5%=200万円
▼こちらの記事も参考になります
【地主&賃借人向け】借地権割合とは?割合の調べ方・実務での活用方法
適切な更新料の考え方
更新料の計算では、更地価格のもととなる借地権割合においても、更新料の割合においても、ケースバイケースで判断しなければなりません。
更新料の実質負担を考える際には、公租公課も考慮する必要があります。更新料は借地権者にとって資産計上される支出で、減価償却が可能です。契約更新期間(通常30年)で均等償却でき、また個人の場合は所得税の計算上、必要経費として算入できる場合があります。これにより実質的な負担額は支払額より低くなることがあります。(詳しくは税理士とご相談ください)
高額な更新料への交渉術と対処法

地主から提示された更新料が高額だと感じた場合、ただ受け入れるだけでなく、適切な交渉を行うことが重要です。更新料は法律で明確に定められた金額ではないため、双方の合意によって決定されます。適正額の見極めから代替案の提案、リスク管理まで、効果的な対処法を専門家と相談して進めるのが良いでしょう。
交渉のポイント
交渉では、タイミングと適正額の根拠がカギとなります。減額を求める場合は、借地契約の期間が満了する十分前前から交渉に着手し、交渉にあたって地価が下落したことを示す根拠資料などを用意することが大切です。
交渉の中で、更新料の額や、返還する場合の条件(原則上は借地人負担となる建物の解体費用など)によっては、地主への借地権の売却や、地主と協力したうえでの借地・底地の第三者への同時売却のほうがよいこともあるでしょう。
交渉自体や事前の調査、最終的にどうすればよいのかといった判断は、借地権の取引事例に精通している専門家の支援を得るのが無難です。
支払いが難しい場合の対応方法
借地契約を維持したくても必要な更新料が支払えない場合、分割払いの交渉や、地主にも利点のある条件の提案が考えられます。手段として検討できるのは、以下の2つです。
■将来の地代減額、もしくは増額抑制と更新料をセットで交渉する方法
……例えば「更新料を満額支払う代わりに、地代を減額させる、もしくは今後10年間は地代を据え置く」といった提案は、地主にとっても長期的な収入の安定につながるため、検討の余地があるでしょう。
■建物の修繕や改良工事を更新料の代わりに提案する方法
……賃借人の住環境を整備する工事(排水設備の改良、境界フェンスの設置など)と更新料の交渉を進めることも検討できます。
支払い拒否した場合のリスク
支払う義務のある更新料の支払いを完全に拒否した場合、最大のリスクは契約更新拒絶の可能性です。借地借家法では借地権者を保護する規定がありますが、更新料の不払いが当初の契約そのほかの事情に基づき「信頼関係が破壊された」もしくは「正当事由」と認められれば、地主側から契約更新を拒絶できる場合があります。
最終的に法定更新等で契約更新が叶ったとしても、最大のデメリットである地主との関係悪化が問題です。将来的な建物の増改築や修繕に必要な同意、災害時の協力関係など、さまざまな場面で地主の協力が必要になるケースは多く、関係悪化によってこれらの協力が得られにくくなる可能性があります。
地主との良好な関係維持のために

借地権の更新料交渉は一時的なものですが、地主との関係は長期にわたって継続します。交渉では、良好な関係を保てるように心がけましょう。
更新料交渉時の注意点
交渉時には感情的にならず、冷静な対応を心がけることが重要です。法的に支払う義務がないということであったとしても、高圧的な態度は「トラブルを起こす人」という印象を与え、交渉を不利にします。あくまでも信頼関係に基づく契約関係であると言う前提で、敬意と感謝の気持ちを示しながら交渉することが、良好な関係維持につながります。
また、口頭での約束と書面による合意は明確に区別する必要があります。交渉の内容や合意事項は可能な限り書面化し、後のトラブル防止に努めましょう。
長期的な視点での地主対応の重要性
地主との良好な関係を維持するためには、定期的なコミュニケーションが欠かせません。季節の挨拶、店舗や住宅の運営状況を定期的に共有することで、信頼関係を深めることができます。
また、地主の高齢化や相続による世代交代も視野に入れた対応が重要です。地主が世代交代すると、これまでの慣行や暗黙の了解が通用しなくなる可能性があります。契約が書面化されていない場合は、書面化を進めることをお勧めします。地主が高齢や相続を理由に底地を手放す意向になった場合、良好な関係があれば借地人が有利な条件で底地を買い取れる可能性も高まります。
最終的に借地権を売却する際にも、地主の協力は非常に重要です。借地権の売却には地主の承諾が必要で、良好な関係があれば円滑な取引が可能になります。また、借地人が底地を買い取る意向を示した場合にも、友好的な交渉ができる環境が整っていることが望ましいでしょう。
まとめ
借地権の更新料は法律で明確に定められたものではなく、契約および土地利用に関する経緯、過去の支払い実績などによってその必要性や金額が判断されます。更新料の支払いを求められた場合は、まず契約書の確認が重要です。
借地権は地主と借地人のとの信頼関係が元となっている契約で成立しているということを再確認しましょう。更新料交渉は一時的なものですが、借地権は長期間にわたって継続するため、将来的な建替えや修繕、災害時の協力などさまざまな場面で地主との関係が重要になります。
感情的にならず、敬意を持った交渉を心がけましょう。契約更新は数十年に一度発生するもので、前回の更新とは全く環境や登場人物が変わっている場合がほとんどです。トラブルになる恐れがある場合は、友好的な交渉のできる借地権の専門家を交えて交渉を進めるのが重要です。