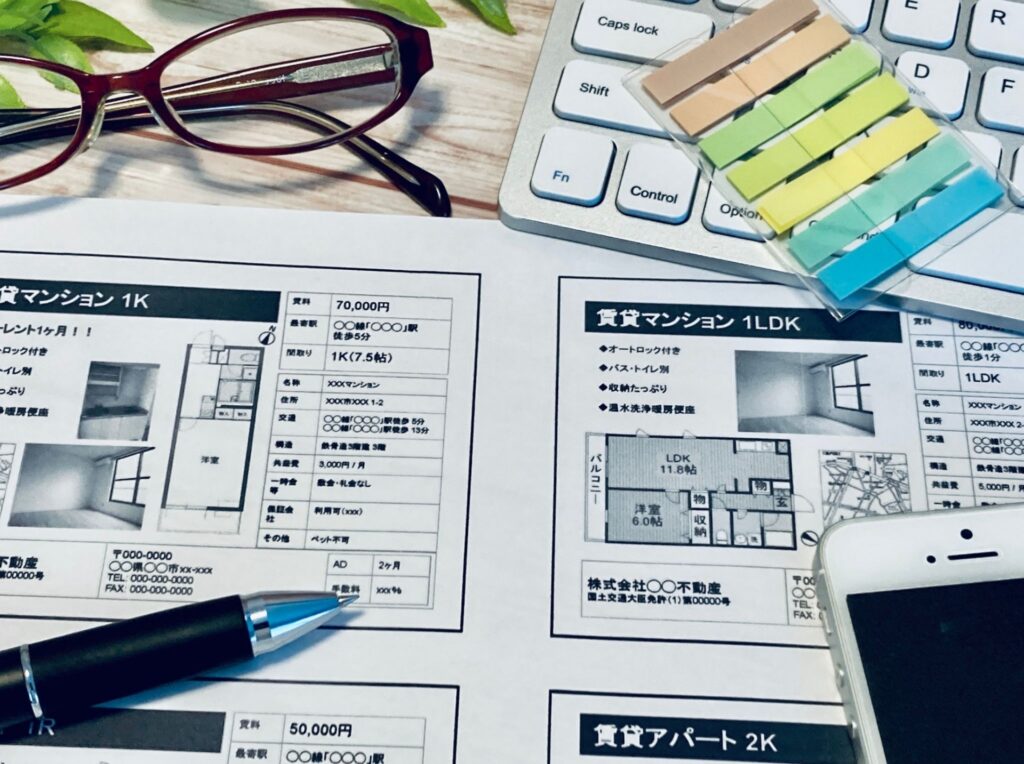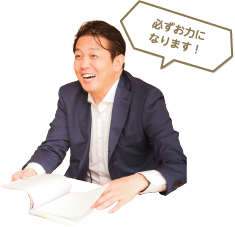親から相続した家について、名義変更(相続を原因とする所有権移転登記)をせずに放置するケースは少なくありません。とくに、相続人が引き続きその家に住み続ける場合は「今までどおり住めるから」と名義変更を後回しにしがちです。こうして手続を遅らせた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
相続登記にまつわる近年の法改正

2024年以降、相続や不動産登記に関する重要な法改正が相次いで施行されます。注意したいのは相続登記の義務化で、家の名義変更をしないことによって思わぬ損失が出る可能性が生じるようになりました。もっとも、ペナルティばかりではなく、登記に必要な情報取得(所有する不動産の調査、特定)を容易にする見直しもいくつか予定されています。
相続登記の義務化(令和6年4月1日~)
相続を知った日から3年以内の登記申請が必須となり、正当な理由なく期限を過ぎた場合は過料の対象に。ただし、遺産分割協議が難航している場合などは「相続人申告登記」という簡易な手続により、処罰を回避することも可能です。
住所変更登記の義務化(令和8年4月1日~)
不動産所有者の住所変更についても、変更から2年以内の登記申請が義務化されます。未申請の場合は5万円以下の過料が科される可能性がありますが、DV被害者への配慮など、一定の例外規定も設けられています。住所変更の義務化により期待されるのは、相続登記を実施するときの負担軽減です。
所有不動産記録証明制度の開始(令和8年2月2日~)
不動産の情報を調べるのに欠かせない登記事項証明書は、個別の物件の情報に基づいて取り寄せるのが常で、所有者の名前による一括取り寄せに対応していません。法改正によって所有不動産記録証明制度が始まると、所有者の氏名・住所から全国一括で不動産情報を調査し、一覧化したものを証明書として交付してもらえるようになります。
相続した家の名義変更をしない場合の6つのリスク

相続した家の名義変更(相続登記)をしないでいると、以下の6つのリスクが想定されます。これらはいずれも、資産価値の低下や予期せぬ損失につながる可能性があるため、早めに対応するよう注意しなければなりません。
相続登記義務化に伴う罰則の対象になる
令和6年4月1日より義務化された相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)については、相続開始を知った日から3年以内に実施しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なお、過去の相続案件についても、令和9年3月末までに手続きを完了する必要があります。
売却・活用ができないまま汚朽が進む
相続した家を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、必ず相続登記が必要です。名義変更をしないままでは、不動産の有効活用ができず、建物の老朽化だけが進んでしまいます。また、賃貸活用や大規模リフォームの際にも、所有者であることを証明できないため支障をきたす可能性があります。
固定資産税が従来の6倍になる
適切な管理がなされず放置された家屋は、地域の「特定空き家」に認定されるリスクがあります。令和5年からは、今後特定空き家指定を受ける恐れのあるものとして「管理不全空き家」の指定も導入されました。管理不全空き家は、1年以上誰も住んでおらず、管理が不十分である場合に指定されます。
上記のいずれかに指定されると、固定資産税の課税につき、それまで適用されていた住宅用地の特例が外れます。その結果、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がり、都市計画税も含めると、税負担は大幅に増加します。
近隣とトラブルになることがある
名義変更をしないまま放置された家屋は、管理不全による近隣トラブルの原因となりがちです。草木の繁茂や害虫の発生、建物の一部崩落など、さまざまな問題が発生する可能性があります。トラブルが深刻化すると、自治体からの改善勧告や、最悪の場合は行政代執行による解体などの対象となり、その費用の償還を求められることも考えられます。
相続人が増えて手続きが複雑化する
相続登記を放置すると、次の世代で相続が発生した際に相続人が増加し、手続が複雑化します。その要因は、時間の経過とともに発生する可能性が大きくなる下記のような状況です。
- 相続人の所在が不明になる
- 認知症などで意思確認が困難になる
- 相続人がねずみ算式に増え、相互に関係が希薄になる
これらの事情が生じると、相続人同士で話し合って合意形成することが難しくなり、相続登記のための書類を集めるなどといった作業に支障が出ます。
早めに登記・売却する場合と比べて損失が増える
相続登記を先送りにすることで、さまざまな経済的損失が生じる可能性があります。その原因として挙げられるのは、不動産の価値低下や維持管理費用の累積に加え、相続人が増えることによる手続費用の増大です。
次に挙げられるのは、好条件で売却する機会の逸失です。時間経過とともに家が古くなれば、それだけ活用に難が生じるようになり、買主に敬遠されやすくなります。売れたとしても、相続から時間が経ちすぎると、譲渡所得につき適用できる3,000万円控除などが適用できなくなり、手元に残る利益が減る問題は見逃せません。
まとめ
相続した家の名義変更は、できるだけ早期に対応することが望ましい手続きです。令和6年4月からは義務化され、放置すると過料の対象となるだけでなく、資産価値の低下や管理コストの増大など、さまざまなデメリットが生じる可能性があります。専門家に相談するなどして、計画的に手続を進めることをおすすめします。