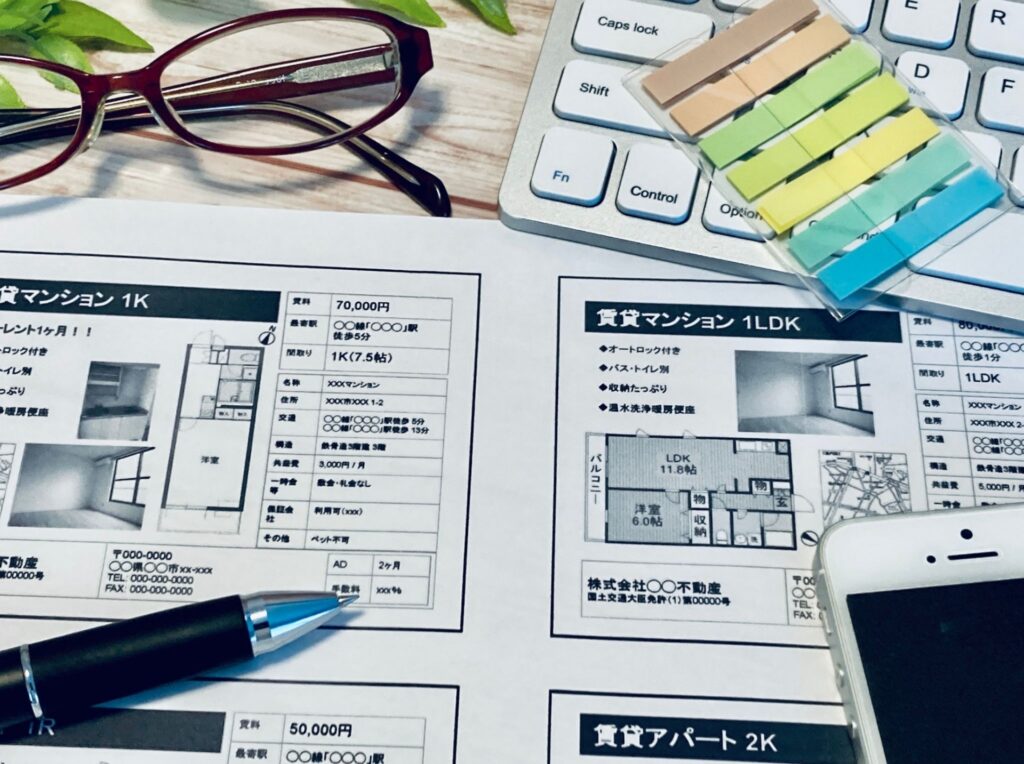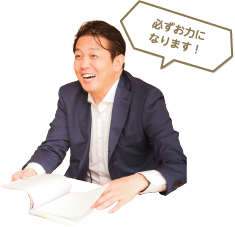借りている土地が負担になる場合などは、その権利(借地権)を地主や第三者に売却することが可能です。ここでは、借地権を手放すときのポイントとなる売却方法から価格の相場、地主との交渉を中心に理解しておきたいポイントを解説します。
借地権売却の主な方法
借地権を売却する方法は主に3つあります。地主への売却、第三者への売却、そして買取業者への売却です。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。ここでは各売却方法の特徴と流れを解説します。
地主に売却する
合意が得られるのであれば、地主に借地権を買い取ってもらうのがもっともシンプルです。この方法の最大のメリットは、このあと解説する譲渡承諾料が不要となるメリットがあります。通常、第三者への売却では目安として借地権価格の10%を地主に支払う必要がありますが、地主自身が買主となる場合は原則として左記の承諾料は発生しません。
また、手続きも比較的簡略化されるため、売却までの時間も短縮できます。価格面では、一般的に更地価格の50%程度が目安とされていますが、立地条件や契約内容、建物の状態などによって大きく変動します。
第三者に売却する
第三者(買取業者を含む)への借地権売却では、まず地主の承諾が必要です。承諾なしに売却契約を結んでも、地主に対抗できないためです。売却の流れとしては、まず地主に売却の意向と買主候補を伝え、承諾を求めます。買主と売買契約の締結は地主の承諾後となり、譲渡承諾料を支払った後に代金決済と権利の引き渡しを行います。
売買契約時には地主の承諾書が必要となり、これがないと登記(=登記簿上の権利者の変更)ができません。譲渡承諾料は一般的に借地権価格の約10%程度が相場ですが、地域や物件の状況によって変動します。この承諾料は借地権者負担となるのが一般的であり、交渉内容によって買主と分担するケースもあります。
借地権の売却価格の計算方法
借地権売却で注意したいのは、一般の不動産と比べて流動性が著しく低く、価格も通常の不動産よりも大幅に低くなります。売却価格については下記の算定で判断するのが一般的で、算定に必要となる「借地権割合」は60%から70%となります。
▼借地権の売却価格の一般的な算定方法
更地価格 × 借地権割合 × 流動性減価-承諾料-建物の解体価格
流動性減価は借地権特有の要素で、買い手が限られることによる価格の下落を意味します。これにより、理論上の価格からさらに20%から30%程度下がることも珍しくありません。地主に売却する場合は、流動性の問題の影響が低くなるため、第三者への売却よりも高い手取りに期待できます。
仲介専門の不動産会社に相談するとき注意点
仲介(買主の探索・契約の仲介)を専門とする不動産会社による査定では、借地権の個別性が十分に考慮されず、実際より高い価格が提示されることがあります。このような査定結果を過信すると、価格水準が折り合わず、売却活動が長期化したり、最終的に大幅な値下げを余儀なくされたりするかもしれません。
一方で買取サービスを利用するときは、上記の過程もあいまち、妥当な価格より著しく低い売却価格となるケースが多々見られます。借地権売却を検討する際は、専門知識を持つ不動産会社に相談し、現実的な価格設定をすることが重要です。
地主との交渉・承諾獲得のポイント

借地権売却にあたって地主の承諾を得るにあたっては、適切な交渉が不可欠です。地主との良好な関係構築や専門家の助言を得ながら、効果的な交渉を進めることが売却成功の鍵となります。
譲渡承諾料の相場と交渉のコツ
譲渡承諾料の一般的な相場は借地権価格の10%程度と解説しましたが、地域や立地条件などによって異なります。都心部や商業地域では20%から30%となるケースもあれば、郊外や住宅地では5%程度に留まることもあります。
交渉に臨む前には、自分が譲れない条件と妥協できる条件を明確に整理しておきましょう。また、借地契約書内に譲渡承諾に関する規定がないか確認することも大切です。契約書に明記されている場合は、その条件に基づいて交渉を進められます。さらに、借地契約の更新時期が近い場合は、更新料と譲渡承諾料の同時請求の可能性も考慮する必要があります。
交渉は専門知識が必要となるため、借地権に詳しい不動産会社を介して行うことをおすすめします。地主との交渉経験が豊富であり、適切な承諾料の提案や交渉の進め方について的確な支援が得られます。
承諾が得られないときの対応策
地主から承諾が得られない場合の対応策として「借地非訟」という法的手続きを活用する方法があります。これは借地借家法に基づき、裁判所に対して承諾に代わる許可を求める手続きで「承諾代諾許可申立て」とも呼ばれます。地主が不合理な理由で承諾を拒んでいる場合に適用されますが、この手続きには時間と費用(弁護士報酬など)がかかるうえ、地主との関係が悪化するリスクもあるため、慎重に検討する必要があります。
別の対応策としては、ほかの買い手への打診も考えられます。とくに借地権の取り扱いに慣れた専門業者であれば、地主との交渉をスムーズに進められる可能性があります。また、地主が承諾を渋る理由を丁寧に聞き取り、交渉条件を再検討して代替案を提示することも効果的です。
借地権売却のポイントと注意点

借地権の売却は、通常の不動産取引とは異なる特有の注意点が存在します。とくに、相続によって取得した場合の手続きや売却後の税金については、事前にしっかりと理解しておきましょう。
相続した借地権は売却前に登記する必要がある
元々の借地権者が亡くなり、親族が権利者となって売却を希望するときは、事前に相続を原因とする借地権建物の所有権移転登記(相続登記)を実施しなければなりません。この手続きによって登記簿上の権利者が変更され、借地権の買主へと権利を移転する準備が整います。
借地権建物の相続登記では、現状の登記情報を確認したのち、遺産分割協議書や遺言書(原則として検認済のもの)を用意しなければなりません。
借地権の売却代金には譲渡所得税がかかる
借地権を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。課税対象となる譲渡所得は、売却価格から取得費および譲渡費用を控除した額です。取得費は、借地権を取得した際にかかった費用(購入代金や契約時の権利金など)ですが、不明な場合は売却価格の5%を概算取得費とすることができます。譲渡費用には、仲介手数料や印紙税などが含まれます。
税率は、借地権の所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、長期譲渡所得の方が低い税率(所得税15.315%、住民税5%)が適用されます。
なお、一定の要件を満たせば、所有権を売却する場合と同様に税負担を軽減できる特例があります。代表的なものとして、居住用財産(マイホーム)を売却した場合の3,000万円特別控除があります。相続した借地権を一定期間内に売却する場合は「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」が適用できる可能性もあります。
譲渡所得税の詳細については、税理士と相談のうえで判断しましょう。
まとめ
借地権は売却可能ですが、地主への売却と第三者への売却のいずれにおいても、地主の承諾や譲渡承諾料、税金など、特有のルールや注意点があります。適正な価格を把握し、地主と良好な関係を築きながら交渉を進めるようにしましょう。
借地権の取扱いでは、底地の権利を持っている場合と異なり、評価や当事者の関係において状況が複雑化しがちです。売却そのほかの手続きを検討するときは、資産整理や権利の取引について知見のある不動産会社に相談すると良いでしょう。